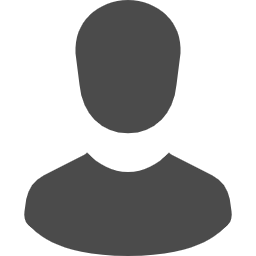デイリーコラム
「老朽インフラの維持管理で注目されるITモニタリング➁」
■ITモニタリング対象
インフラモニタリングでの主対象となる橋梁、道路及びトンネルの概況を記載する。主要インフラである橋梁及びトンネルでは、2020年以降に建設後50年を超えるものが急速に増える見通しであり、この両施設がインフラモニタリングで最大のターゲットになる。
◇橋梁
・橋長2m以上の橋梁数は全国で約70万橋
・管理者別構成は、市町村68%、政令市7%、都道府県19%、国4%、高速道路会社2%
・市町村が管理する橋梁(約48万橋)の中で、通行止めや通行規制が掛っているところが約2,000ケ所。この数は、毎年10%以上の割合で増えている(5年で倍増)
・現在では、町の50%、村の70%で土木技術者がいない、もしくは不足していると見られる
・2020年代以降、全国橋梁で一斉に建設後50年超となることから、予防保全的な橋梁マネジメントニーズが不可欠になった
◇トンネル
・道路トンネル数は全国で約10,300本
・管理者別構成は、市町村23%、政令市3%、都道府県46%、国13%、高速道路会社15%
・国交省及び高速道路事業者が管理しているトンネルのうち、高度経済成長期に建設されたものが全体の25%を占める
・国交省が策定した「道路トンネル定期点検要領(2014年6月)」では、定期点検の実施頻度を5年に1回としている
◇道路
・道路タイプ別では、高速道路9,351km、一般国道66,657km、都道府県道143,046km、市町村道1,066,459kmで、道路総延長は1,285,431k
・全体の83.0%が市町村道で圧倒的な比重。以下、11.1%が都道府県道、一般国道は5.2%、高速自動車国道は0.7%と構成比的には若干程度
・高速道路及び直轄国道などでは、ほぼインフラの維持管理に向けた取り組みがなされている。しかし市町村道などでは予算的な制約もあって、維持管理でのカバー率は低い
※続くかもしれない
「老朽インフラの維持管理で注目されるITモニタリング①」
日本のインフラストックは累計800兆円超と言われているが、その老朽化が急速に進展している。民間の鉄道や高速道路事業者などでは、維持管理(安全・安心)・モニタリングへの資本投下は一定水準が維持されているが、一方で行政(国や自治体など)の関連予算は中・長期的には厳しい状況が予想される。そのため老朽インフラ対応では、特に地方自治体を中心とした行政の取り組みは課題になる。
現在、日本の債務残高(国と地方を含めた長期債務残高)は1,000兆円を超えており、これに借入金や政府短期証券を含めるとゆうに1,500兆円前後にたっする規模になる。このため、債務残高のGDP比では主要先進国の中では極端に大きな比率を占めている。加えて、日本の高齢化率(65歳以上人口比率)は世界トップクラスで、当然、今後の社会保障関連予算の膨張も見込まれる。
このような財政状況ではインフラの新設は難しく、必然的に既設インフラの長寿命化が重要になる。しかし目視点検をベースとした座組では、人的・予算的な制約もあって、全インフラを点検することは不可能である。現実には、点検や保全対応ができないインフラも出ている。
ここでIoTを始めとしたITテクノロジーをベースとした「ITモニタリングビジネス」が注目される。この仕組み(予防保全的な仕組み)の導入で、インフラの維持管理に係る保全コストの抑制、業務効率の向上・省人化、さらには老朽インフラ対応問題の改善が期待できる。つまり既設インフラの寿命延長を実現することで、従来とは違ったメンテナンスサイクルを創出するのである。
※続く
「事故防止を目的に「健康支援×運転」を結びつける動き」
自動車事故の予防文脈において、ドライバーの健康状態を起点に安全運転を促す取り組みが広がっている。特に損害保険会社やテレマティクス関連企業の間では、認知機能や脳健康、PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)などの健康支援サービスと連携する動きが活発化している。
直近ではアクサ損害保険が2026年1月、自動車保険契約者向けに「スマート脳ドック」「MVision health」「あたまの健康チェック」の特別価格紹介を開始したと発表しており、疾病起因事故や高齢運転者の認知機能低下に対応し、脳・認知の定期チェックを促す施策として位置づけるとのことである。
損保ジャパンは2025年10月、東京医科大学発スタートアップMEDEMILと業務提携を行うと発表しており、ドライブレコーダー等の運転挙動データと眼球運動解析「MEDEMIL Drive®」を組み合わせ、運転能力を科学的に多角評価する枠組みの構築を目指すとした。高齢ドライバーの安全運転支援や職業運転者の就労継続、ライドシェア領域まで視野に入れた展開になるとのことである。
損保系に限らず、運行管理プラットフォーム側の連携も動いている。都築電気は2026年1月、クラウド型動態管理サービス「TCloud for SCM」とharmoの運輸向け健康支援ソリューションの統合提案を開始したと発表しており、将来的な機能・データ連携も見据え、PHR×運行管理で“健康起因の事故ゼロ”と現場の負荷軽減を狙うとのことである。
背景には、運転寿命の延伸とドライバー不足の深刻化がある。健康リスクを放置すれば事故や逸走、急な離職につながる一方、早期の気づきと支援により「運転を続けられる期間」を伸ばせる可能性がある。 今後の焦点は、これらの仕組みが“現場で使い続けられるか”である。導入の発表で終わらせず、日々の運用にきちんとなじむか。その「定着」が、この取り組みの価値を決めるだろう。
「組立型保険が広がる-多様な生き方に寄り添うかたちの保険」
近年、生命保険で必要な保障を組み合わせる“組立型”の設計が改めて広がっていると感じる。背景には、ライフスタイルの変化や医療環境の多様化があるとみられる。
例えば大手生保では、日本生命の「ニッセイ みらいのカタチ」が複数の保障から選んで組み合わせる商品として長く展開されており、明治安田生命の「ベストスタイル」も特約を組み合わせ、更新タイミングで見直しができる“組立総合保障”として位置づけられている。富国生命の「未来のとびら」は、主契約に縛られず特約を自由に選ぶ複合型保障で、死亡・介護・就業不能・がんなどを必要に応じて組み合わせられる点が特徴である。
こうした設計は“パッケージのまま加入する”という従来型から、“生活の変化に合わせて保障を足し引きする”という考え方へのシフトともいえる。世帯構成や働き方が多様化する中で、死亡保障より医療・介護・就業不能を重視する家庭も増え、保障の優先順位は個人ごとに異なる。組立型はその違いに対応しやすい。
また、組立型が増えているのは医療分野でも同様だ。アフラックは2025年12月、新医療保険「あんしんパレット」を発売し、特約1つから加入できる柔軟な設計を打ち出した。治療給付金・通院・先進医療などを目的別に選べ、既存保険の“足りない部分だけ”補う使い方も想定されている。
医療環境の変化(入院の短期化や外来・通院中心の治療の増加、先進医療の普及など)も、この流れを後押ししていると考えられる。従来の「入院日額」中心では拾い切れない費用が増え、診断一時金型・月額型治療給付・通院保障のニーズが高まっている。
もっとも、組立型の“選べる自由”は“選ぶ難しさ”とも表裏一体であるといえる。営業職員や保険ショップで相談しながら、自分の生活に必要な保障は何かを整理することが欠かせない。組立型保険の拡大は、多様な生き方に合わせて“保障をつくる”という発想が定着しつつあることの表れである。今後はさらに、保障の選び方を分かりやすくする工夫や、比較しやすい情報提供が求められるだろう。
【今週の"ひらめき"視点】2025年の経常収支、過去最高を更新。海外投資収益の拡大が寄与
当社代表が最新のニュースを題材に時代の本質、変化の予兆に切り込みます。
2月9日、財務省は2025年の国際収支状況(速報)を発表した。輸出は半導体部品や食料品が好調で107兆7,630億円(前年比+2.5%)、輸入はエネルギー価格の下落もあり108兆6,118億円(同▲0.1%)、差し引き8,487億円の赤字となったが赤字幅は前年比+2兆8,115億円と改善された。サービス収支は、旅行収支の6兆3,429億円、アニメ等のコンテンツを含む知的財産収支における3兆1,732億円の黒字を巨大IT企業への支払など所謂“デジタル関連支出”が飲み込み、3兆3,928億円の赤字となった。
結果、「貿易・サービス収支」は4兆2,415億円の赤字、一方、経常収支全体は31兆8,799億円の黒字、2年連続で過去最高を更新した。海外子会社からの配当など直接投資収益が拡大したことにより第一次所得収支が前年比104.7%、41兆5,903億円と過去最高となったことが主因である。
日本貿易振興機構(ジェトロ)の「2025年度海外進出日系企業実態調査」(2025年11月)によると2025年に黒字を見込む海外進出日系企業の割合は66.5%(前年比+0.6%)、大企業では7割を越える。地域別ではUAEが83.3%、豪州、韓国、ブラジル、南アフリカ、インドも75%を越える。一方、トランプ関税の影響を受ける米国やメキシコ、低成長が続く中国、インドネシアでは3割以上が営業利益の悪化を見込む。しかし、後者にあっても黒字企業の割合は6割を越える。第一次所得収支で稼ぐ国際収支の構造は不変ということだ。
自由貿易への信任が失われつつある中、産業政策の論点は“経済安全保障”に向かう。確かにここ数年、パンデミック、相手国の政治・経済環境の急変、地政学リスクの拡大など、海外投資の不確実性とリスクが顕在化した。仕入先や販路の分散が難しい中小企業、新興国の成長コストに耐えられない企業にとって“撤退”の判断は止むを得ない。ただ、国内回帰ですべてが解決するわけではない。グローバル経済におけるプレゼンスの拡大もまた戦略的BCPであり、すなわち経済安全保障投資である。要するに個々の企業の収益力向上こそが総体としての安全保障の礎になるということである。
今週の“ひらめき”視点 2026.2.8 - 2.12
代表取締役社長 水越 孝
「『東京ポイント』の付与が開始、開始日に受け取ってみた」
2026年2月2日より、「東京アプリ生活応援事業」が始まっています。同事業は、物価高が続く中で都民の生活を応援することを目的に実施され、都内在住者は「東京アプリ」のダウンロードおよびマイナンバーカードによる本人確認を完了することで、11,000円分の「東京ポイント」を受け取ることができます。
私も、開始日にアプリのダウンロードとマイナンバーカードによる本人確認を行い、数日後に無事ポイントを受け取ったのですが、マイナンバーカードによる本人確認で少し躓きました。本人確認の際に、マイナンバーカードを作成したときに決めた「利用者証明用電子証明書」の暗証番号と「券面事項入力補助用」の暗証番号(どちらも4桁の数字)が求められるのですが、この後者の番号を完全に忘れてしまっていたのです。結局、何とか正しい番号にたどり着き、本人確認を終えられましたが、3回間違えるとロックがかかり、区役所等での手続きが必要になるとのことで大変緊張感がありました(私が正解にたどり着いたのは3回目)。ちなみに、この2つの暗証番号は同じ数字を使うことも可能であるそうなので、どうしても片方を思い出せない方は同じ数字を試してみると良いかもしれません。
受け取った「東京ポイント」は民間決済事業者のサービスと交換でき、2026年2月10日時点では楽天ペイ(楽天キャッシュ)、Vポイント、dポイント、au PAY、メルカリポイントとの交換が可能になっているほか、PayPayポイント、WAON POINTも交換先に追加されることが発表されています。各事業者では、「東京ポイント」からの交換でポイント増量キャンペーンや、抽選で追加ポイント進呈キャンペーンなどの施策も展開されているので、交換前のご確認をおすすめします。
【アナリスト便り】「2026アフィリエイト市場の動向と展望」を発刊
2026年1月30日『2026アフィリエイト市場の動向と展望』を発刊いたしました。
本レポートでは、2025年度のアフィリエイト市場が、AI技術の急速な浸透やSNS・ショート動画プラットフォームの存在感の高まりを背景に、大きな転換期を迎えている状況を踏まえ、市場構造の変化と今後の展望について分析しております。
生成AIの進展により、コンテンツ制作や記事品質の向上、広告運用の効率化が進み、ASPやメディア事業者のワークフローは大きく変化しつつあります。また、TikTok Shopの日本市場におけるサービス開始を契機として、SNS・動画を起点とした購買行動が新たな領域として拡大し、アフィリエイトの成果発生源も多様化しています。
一方で、生成AIやAI Overviews(AIによる検索要約)の登場により検索環境が変化し、トラフィック構造にも影響が生じています。特にSEOメディアにとっては流入環境の不安定化が進んでおり、SEO依存度の高いASPや広告主にとっては重要な課題となっています。
本レポートでは、これらの市場トピックスを踏まえ、主要ASPの事業動向、メディア構造の変化、AI時代におけるASP事業者の競争優位戦略、さらには中期的な市場成長性について、多面的な視点から整理・分析を行っています。関連市場の把握や事業戦略立案の基礎資料としてご活用頂ければ幸いです。
★FinTech Journalに寄稿しました★
Webメディア「FinTech Journal」にて、1月20日付けで、「2026年において保険業界で注目される10個のトレンド」を挙げる記事を寄稿させて頂きました。悩んだ挙句、なんとかかんとか10個に絞っております。
反応はよいようで、お陰様で多くの皆さまにシェア頂き、また、多くの方々に読んで頂いているようです。日々、取材を通じて、生成AIでは決して取得できない「一次情報」をベースに記載しております。ぜひお手すきの際に、ちょっと覗いていただけますと幸いに存じます。
【今週の"ひらめき"視点】米中、世界の2大強国を怒らせたグラミー賞にStanding ovation!
当社代表が最新のニュースを題材に時代の本質、変化の予兆に切り込みます。
2月1日、米音楽界最高の栄誉「グラミー賞」の第68回授賞式が開催された。年間最優秀楽曲はビリー・アイリッシュの「WILDFLOWER」、年間最優秀アルバムはバッド・バニーの「DeBÍ TiRAR MáS FOToS」が受賞した。年間最優秀楽曲を3回受賞したのはアイリッシュがはじめて、また、全曲がスペイン語で歌われているアルバム(バニー)がグラミー賞の主要部門に輝いたこともはじめてであり、話題となった。
授賞式恒例のスピーチでは「奪われた土地に不法な人間は存在しない」と語ったアイリッシュを筆頭にトランプ政権のもとで先鋭化する移民・税関捜査局(ICE)に対する批判が相次いだ。トランプ氏を不快にさせるにはこれだけで十分であろうが、司会のトレバー・ノア氏は性犯罪で起訴され拘留中に死亡した富豪エプスタイン氏とトランプ氏との関係を暗示させつつ「グラミー賞はアーティストなら誰でも欲しがる。トランプ氏がグリーンランドを欲しがるように」と揶揄、これに対してトランプ氏は「グラミー賞は見るに堪えない」「ノアを訴える」とSNSに書き込んだ。まさに“アメリカの分断”を象徴する一幕だ。
一方、“最優秀オーディオブック、ナレーション、ストーリーテリング・レコーディング賞”にはチベット仏教の指導者ダライ・ラマ14世が自身の思いを英語で語ったアルバム「Meditations」が選ばれた。意外に思われる方も少なくないと思うが、彼は2020年にも音楽と読経を融合させたアルバム「Compassion」を発表している。因みにこのアルバムにはアヌーシュカ・シャンカールがシタール奏者として参加している。彼女はノラ・ジョーンズの異母妹で、父はビートルズとも親交のあったラヴィ・シャンカールである。余談ながらラヴィもまたジョージ・ハリスンとともに主催した1971年の「バングラデシュ難民救済コンサート」で第15回グラミー賞「最優秀アルバム」を受賞している。
話を元に戻そう。トランプ氏に続いてグラミー賞に噛みついたのは言うまでもなく中国当局である。「Meditations」の受賞に対して中国外務省は直ちに声明、「芸術に関する賞を反中国の政治的道具に利用した」とグラミー賞を批判するとともに、ダライ・ラマ14世を“宗教家の衣を被った政治活動家”と非難した。言わば世界の2大大国を敵に回した感のあるグラミー賞であるが、つまりは音楽の力の証左ということだ。あらゆる政治的、宗教的、思想的、地政学的フィルターを外し、「平和、環境、人類の結束への思いやりと理解が世界の幸福につながる」(ダライ・ラマ14世)とのメッセージを素直に受け止めたい。
今週の“ひらめき”視点 2026.2.1 - 2.5
代表取締役社長 水越 孝
【発刊裏話】「2025 衛星データ活用ビジネスの実態と展望 ~分野別/用途別の衛星データ活用実態の徹底分析~」
2025年4月に、「2025 衛星データ活用ビジネスの実態と展望 ~分野別/用途別の衛星データ活用実態の徹底分析~」というタイトルのレポートを発刊しました。
ここでは、「衛星vsドローン」といった競争構造を想定したマーケット分析を行いました。しかし今回のドローンレポートを編集してみて、考え方が変わってきました。この両者は対立する部分もありますが、大枠としては「棲み分けが図られる可能性」が大きいと考えられます。例えば、俯瞰して見る場合には衛星画像を、より細部を詳細に見る場合にはドローン画像を使うといったイメージです。
衛星データレポートを発刊して1年にも満たないのですが、今回のドローンレポートで、両者の関連性は完全に上書き修正されました。
【アナリスト便り】「2026 ドローンソリューションビジネスの実態と展望 ~社会インフラ/エネルギー、設備点検、建設・土木、農業などでのドローン活用~」を発刊
2026年1月22日、「2026 ドローンソリューションビジネスの実態と展望 ~社会インフラ/エネルギー、設備点検、建設・土木、農業などでのドローン活用~」を発刊しました。
本レポートでは、農林水産分野(農薬・肥料散布など)及び社会インフラ分野(鉄塔点検など)を中心としたドローン活用/ドローンソリューションの現状を踏まえた上で、法規制や制度改正の流れ、AIや5G、ドローンプラットフォームといったテクノロジー面も勘案して、2030年に向けた分野別のマーケット展望を行ったものです。
今後は、「ドローン×AI」の座組が浸透することで、ドローン活用サービス/ソリューションは高度化すると考えます(ドローンのポテンシャルを高める)。またドローン本体の低廉化/高機能化、セルラーネットワークの利活用、ドローンプラットフォームの普及、衛星との連携拡大なども奏功要因と言えましょう。さらに外部環境として、現場作業者の高齢化及び人手不足、ノウハウ継承問題、さらには就労環境面での働き方改革/ワークスタイル変革志向などがあり、現場の自動化・省人化を目的としたドローン活用には追い風が吹いています。
今回は新規テーマとして発刊したマーケティング資料ですが、ぜひ関連マーケット評価、分析における基礎資料として活用してください。(早川泰弘/川口御生)
2026 ドローンソリューションビジネスの実態と展望 ~社会インフラ/エネルギー、設備点検、建設・土木、農業などでのドローン活用~ | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所
「情報処理技術者試験 大幅刷新」
経済産業省が、2027年度をめどに情報処理技術者試験を大幅に刷新することを発表しました。現行試験の試験内容は8つに細分化されていますが、刷新後は、システム領域、データ・AI領域、マネジメント・監査領域の3つのスキル領域に集約することが検討されています。
背景には、AIの高度化で1人の技術者がより広範な領域を担えるようになったこともあるようですが、ITベンダの技術者がユーザ企業の担当者に伴走することも求められるようになり、より広く知っていることが両者のコミュニケーションの活性化に繋がれば、という狙いもあるようです。
取材でも、ITベンダとのコミュニケーションを課題とするユーザは多いのを感じます。この課題が少しでも解消される刷新に繋がれば良いと思います。
【短期集中連載】生成AI/AIエージェントレポート発刊コラム⑫:『隠しきれない生成AI感 』(終)
「これ、生成AIで作成された雰囲気あるな」と感じることはしばしばある。生成AIによって生成されたコンテンツは完成度が非常に高い。基準はともかく、テキストであれ画像であれ、90点くらいはあるのではないかと感じている。ただ、この90点の取り方が人間とは違う。生成AIは全体を通じて無難に90点を取っているように見える。人間が作成したコンテンツの場合、得手不得手が見えるのだと思う。例えば、誤字脱字はありつつも例示がユニークで非常に分かりやすい文章であったり、背景は上手くないが人物の表情は豊かな絵がある。同じ「90点」でも、全体を通じて無難に90点を取るAIと、全体を平均して90点を取る人間、という違いなのではないかと思う。
あえてプロンプトで表現を調整することもできるが、それもまたプロンプトに対して無難な90点を取っている。将来的にAIにも個性のようなものが付いてきたら話は別だが、今この瞬間に感じる人間の強みはここなのかなと思っている。
【今週の"ひらめき"視点】株式市場改革、上場会社は“公開企業”であることの意味を問い直せ
当社代表が最新のニュースを題材に時代の本質、変化の予兆に切り込みます。
1月26日、東京証券取引所は「従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会」(第9回)を開催、議決権保有比率が40%を超える大株主※を有する上場会社の取締役選任議案において、大株主とその関係会社票を除いた少数株主の賛否率の開示を義務付ける旨、決定した。あわせて少数株主の反対票が5割を越えていた場合、半年以内に反対理由に関する分析結果を開示するとともに株主との対話方針等の策定を求める。新たな施策は2026年12月期の決算企業から適用する方針だ。
研究会では上場会社の負担増への懸念も議論されたが、最終的に「十分に注目すべき少数株主の反対意見は可決されたことをもって無視すべきではない」との方向でまとまった。昨年、JALの持分法適用会社(株)エージーピーの総会では、大株主JALが提案した“株式併合による非上場化案”に対して、経営側はMoM(マジョリティ・オブ・マイノリティ)議案で対抗した。このケースは「大株主と経営陣との対立」といった構図であり、したがって、大株主が経営の実権を握っていることを前提とした今回の改定案とは条件が異なる。しかしながら、少数株主の権利があらためて注目されたことの意味は大きい。
同日、“上場”を巡ってもう一つ重要な改革が発表された。日本公認会計士協会は「新規上場会社等の会計不正によって財務諸表の信頼性への懸念が高まっている」とし、上場会社監査法人の品質管理システムのモニタリング強化等をはかるとともに、小規模監査法人の監査品質への懸念を払拭すべく、現在“最低5人”とする会計士の人数要件を引き上げると発表した。売上の最大9割が架空取引であったAIベンチャー“オルツ”の事案が対策を急がせたであろうことは想像に難くない。
少数株主との対話、財務諸表の信頼回復は健全な株式市場を維持するための必須条件である。昨年6月の総会に株主提案があった会社は111社、可決はわずか7社に留まる。不適切会計も新規上場企業だけの問題ではない。日本公認会計士協会によると会計不正企業数は年々増えており昨年3月期には56社に及んだ。背景には資本効率の改善、高い株主還元、ガバナンス強化など企業価値の短期向上を求める投資家からの強いプレッシャーがある。上場廃止を選択する企業も後を絶たない。昨年は過去最多の124社に達した。上場会社および上場を目指すスタートアップには“パブリックカンパニー”であることの戦略的意義と覚悟をあらためて問い直していただきたく思う。
※保有率の計算に際しては財務諸表等規則8条8項に定める関係会社を含む(東京証券取引所資料より)
【関連記事】
「3月期決算、株主総会ピークへ。過去最多となった株主提案の行方は?」今週の"ひらめき"視点 2025.6.8 - 6.12
今週の“ひらめき”視点 2026.1.25 - 1.29
代表取締役社長 水越 孝
【短期集中連載】生成AI/AIエージェント生成AIレポート発刊コラム⑪:『チャッピー、愚痴聞いてよ 』
対話型AIに名前つけていますか。OpenAIのChatGPTを“チャッピー”と呼ぶ人は結構いるのではないかと思う。日本人はキャラクター性を大事にする傾向があるように思う。名前や性格が分かると親しみを持ちやすい。取材で聞いた話では、生成AIの利用を促進する手段として各従業員の対話型AIにキャラクターを設定した企業もいるという。それぞれ個別に調整するのは大変である一方で、自分と相性が良い性格だったり、好きなキャラクターに扮した話し方をされると面白いのかもしれない。
私は名前こそ付けていないが、誰かと話しているときに「“自分”のAIはこう答えてる」と言っている。この言い回しが自然に出る時点で、対話型AIが “いつもの相談相手”として定着し始めているのかもしれない。人格があるわけではないと分かっていても、使い方が積み上がるほど、その人なりの「付き合い方」が生まれる。名前を付ける行為は、その入口を作るための工夫なのだろう。
【短期集中連載】生成AI/AIエージェントレポート発刊コラム⑩:『AIの言い合い 』
これまで生成AIの活用領域といえばテキストが中心であった。今回の調査を通じて、次はコンタクトセンターの応答に生成AIを活用していきたいとする事業者が多く見られた。これは音声生成の技術が進歩したことによる影響が大きいのは明らかである。
今後、生成AIがコンタクトセンターで活用されるメリットを考えると、第一に人手不足の解消が挙げられる。第二にカスハラ対策である。以前、全く異なる調査で、支払い催促の電話にAIを活用したことで担当者の心理的負担が軽減しただけでなく、支払いに応じる割合も高くなった事例もあるとうかがった。電話の受け手もAI相手に怒鳴るようなことはしないし、AIであれば懲りずに催促してくる。
とはいえ、近い将来では生活者の電話の一次対応も生成AIが応じるような世界観にもなっている気がするので、AI vs AIが行われる未来まで見える。AIがAIに対して敬語を使って言い合いする可能性すらあるわけで、これでは肝心の人間だけが蚊帳の外である。
【短期集中連載】生成AI/AIエージェントレポート発刊コラム⑨:『一旦、使ってみるかで良い 』
2025年のM-1では画像生成を活用した企画が実施されていた。企画に関して賛否あるのは置いておいて、生成AIが日常に入り込んでいるんだなと感じた。
さて、企業における生成AI活用も浸透している。調査では既に4割の企業が生成AIを活用している。中には、とりあえず生成AIを導入してみるという企業もある。こうした先端技術の活用において従来は、技術を使うのではなく、課題に対して最適な技術を選択すべきだと指摘されてきた。基本的な考え方は生成AIも同様である。
一方で生成AIの場合は「とりあえず使ってみる」が迎合されている傾向にある。ユーザ側で活用方法を考えられるほど自由度が高いこと、初期投資を抑えられること、そして自然言語で扱えることが要因だろう。取材では北米は日本よりも積極的な投資が行われている。これは具体的な効果見込みよりも、将来的に企業にとって必要な技術であると確信しているからではないか、という話を聞いた。最終的には課題に対して最適な技術か検討するとして、まずは入れてみて、手応えがなければ一度寝かせる判断もありだろう。利用が拡大している以上、「最初から使わない」という選択はリテラシー格差を生んでしまう危険がある。
【短期集中連載】生成AI/AIエージェントレポート発刊コラム⑧:『削減された工数はどこに? 』
【生成AIを活用したことで年間○○時間の削減を実現しました!!】は、よく見るタイトルである。これ自体は非常に意味のあることだと思っている。一方で、ここで削減された時間なり工数はどこにいったのか、というのも気になる。
今後、事務作業の自動化が進んで工数削減が実現できたとして、単に人材を削減してしまうのか、それら人材をリスキリングして新たに活躍できる場を設けるのか。これは大きな差ではないか。人手不足が深刻化していく中で、新たな人材を確保することは容易ではない。会社に慣れた人材を再配置できれば、事業の拡大も見込める。削減した工数や時間を再分配したことで、事業や売上の拡大が見込めます、までいけると導入の効果が大きく見える。そんな部分まで示せると、導入検討ユーザとしてもありがたいのではないかと思う。
【今週の"ひらめき"視点】ファッション市場の構造変化にみる日本の今。内に閉じるな、外へ
当社代表が最新のニュースを題材に時代の本質、変化の予兆に切り込みます。
1月19日、イタリアの高級ブランド“ヴァレンティノ”の創業者ヴァレンティノ・ガラバーニ氏が亡くなった。1960年代前半、フィレンツェでファッションショーを開催、イタリアのオートクチュール界の先駆けとしてのキャリアを本格的にスタートさせる。1968年には有名な「ホワイトコレクション」を発表、トレードマークとなる“V”のロゴもこの頃から登場する。
1980年代から90年代後半、“ワンランク上”がマーケティングの主流だった時代、本家にあやかった多くの“バンレチノ”が量販店に溢れた。百貨店の市場規模(日本百貨店協会)が11兆円を超えた1997年、この年の月間現金給与総額(事業所規模30人以上、毎月勤労統計調査より)は421,324円となった。しかし、ここをピークに分厚い中流層は崩れてゆく。2024年の月間給与総額は397,789円(同)、百貨店市場も6兆円を割り込んだ。この間、繊維製品小売市場も14兆5288億円から10兆9452億円に縮小、国内市場の主役は売上高を12倍へと飛躍させた“ユニクロ”に取って代わった。
一方、インポートファッション市場は1997年の1兆6612億円から2024年には2兆4714億円へ拡大、リーマンショック等による一時的な足踏みはあったものの年平均成長率は1.5%と堅実に成長している。とは言え、需要構造は変わった。バーバリーの戦略転換がこれを象徴する。2015年、バーバリー本社(英)は三陽商会とのライセンス契約を打ち切り、販路を直営店に一本化する。もちろん商品はインポートのみ、日本国内におけるシェアを捨て、富裕層とインバウンドにターゲットを絞り込んだグローバル戦略に振り切った。
果たして結果は、2024年、バーバリーの国内売上高は2015年比約2倍へ、ヴァレンティノもまた約2.5倍へ倍増させている。この10年、国内富裕層は一貫して増加、インバウンド市場の拡大もご承知のとおりである。ジャパン・クオリティを支えてきたのは国内の良質なベターゾーンマーケットである。今、内需の量的な縮小が避けられないのであれば、グローバル市場における競争力の回復こそ“安い日本”から脱する鍵だ。引き籠もっている場合ではない。
※アパレル市場、インポートブランド市場に関するデータは当社調査資料「繊維白書」、 「アパレル産業白書」、「インポートマーケット&ブランド年鑑」から引用
今週の“ひらめき”視点 1.18 - 1.22
代表取締役社長 水越 孝
【短期集中連載】生成AI/AIエージェントレポート発刊コラム⑦:『アバターとクローンの境界線 』
調査を通じて感じたのは技術ができることと、やってよいことは同じではないということである。生成AIの進化で、人間そっくりなアバターや音声を体験できる場面が増えてきた。
便利である一方、どこからが「やりすぎ」なのかは決めにくい。著作権など法の話は分かりやすいが、もう一段手前に倫理の問題がある。たとえば、本人がOKと言えば何でも許されるのか、本人が亡くなっている場合は誰が決めるのか、周囲の人が強い違和感を持つ使い方はどう扱うのか。リアル空間のクローンとデジタル空間のアバターは別物だと言っても、見た目や声が近づけば境界はあいまいになる。
だからこそ、法律の整備を待つだけでなく、「本人の同意」「利用の範囲」「悪用された時の責任」まで含めて、倫理面のルール作りも同時に進める必要があるのではないか。
【短期集中連載】生成AI/AIエージェントレポート発刊コラム⑥:『「見えない手順」を捕まえる 』
生成AI市場では本人を代替するアバター「AI上司」といった考えがある。これは究極的には、本人の記憶や感情を学習したアバターが動くことになるのだろうか。ややSFな話ではあり、実現するためにはドキュメントだけではなく、本人の経験や勘も学習に必要である。容易な話ではない。
こうした高度な活用に限らず、暗黙知を学習させることは市場における大きな課題になっている。現在の業務が円滑に動いているのは、業務に慣れ親しんだ人材が無意識に効率化させている暗黙知の存在がある。これには本人も言語化できない内容も含まれている。これをデータ化する方法は、作業風景の録画やインタビューなど様々である。
暗黙知の収集に正解はない。ベンダとしてもとにかく試して多くの方法を持つことが今後のサービス展開においても重要になるだろう。
【短期集中連載】生成AI/AIエージェントレポート発刊コラム⑤:『そのデータ利活用、現場の負担を増やしてませんか 』
生成AIの活用が促進されることでデータの価値が高まっている。取材で印象的だったのが、生成AIの活用を促進したことでデータの整備に取り組む企業が増えたという話である。一方で、このデータ整備は重要である反面、苦労が多い。これまで蓄積してきたデータを整備するのも一筋縄ではいかないが、これから増えるデータもAIに学習しやすい形で蓄積しなければならない。
ここが落とし穴で、ゴールは業務効率化であるにもかかわらず、データを蓄積する方法が既存業務の負荷になってしまっては意味がない。負担を上回る効率化や売上増加が見込めるなら良いが、それらが見込めず、単に生成AIに活用できるかもしれないという見切り発車では現場のやる気もおきない。
生成AIの活用促進によって企業規模を問わずデータ利活用の意欲は高まっている。これまでデータ活用に取り組んでいなかった企業が、こうした事態に陥らないような仕組みを提案することもサービス提供側に求められる。
【短期集中連載】生成AI/AIエージェントレポート発刊コラム④:『無感情な恋愛相談 』
生成AIを日常の相談相手として利用できる。私も冷蔵庫の食材を打ち込んでレシピを考えてもらっている。中高生も日常の相談に利用しているという話を聞く。内容は多岐にわたるのだろうが、どうやら恋愛相談でも利用されている模様である。手軽に相談できる環境なのだから、じゃんじゃん活用したらよいというのが私の考えである。
恋愛は割と感情に近い領域なのかと思っている。“感情”がないとされるAIに“感情”に係る相談をするのは、おもしろい。とはいえ、世の中には恋愛マスターと称される人が、インターネット上にウソかホントか必勝法を公開している。そういう意味では、そうした必勝法(?)の集合知なのだから恋愛もデータなのかもしれない。
恋愛相談はさておいて、AIが心の悩みの相談相手として機能している点は注目すべきである。人には言いにくい内容でも、AIなら躊躇なく投げられる。相談の手段が一つ増えること自体に意味がある。
【今週の"ひらめき"視点】社会との信頼回復に向けて、組織は自浄能力を取り戻せ
当社代表が最新のニュースを題材に時代の本質、変化の予兆に切り込みます。
1月14日、原子力規制委員会は、中部電力が浜岡原子力発電所の再稼働審査において“想定される最大規模の地震の揺れ(基準地振動)”を過小評価していた問題について「データのねつ造」と断定、審査の停止と本社への立ち入り検査を実施すると発表した。IDカードの不正使用(東京電力)、地質データの書き換え(日本原子力発電)、核物質防護センサーの点検記録の虚偽記載(東北電力)など福島第一原発の事故を経てなお原発を巡る不正が止まない。一体、何がそうさせるのか。これは原発事業者に固有の問題であるのか。
浜岡原発におけるデータ不正が発覚したのは2025年2月、公益通報制度を使った原子力規制委員会への“外部”からの情報提供だった。2025年10月、日本取引所グループから「特別注意銘柄」に指定されたニデックの不正会計問題の端緒も海外子会社における不正な利益操作に関する “匿名”の内部通報であった。2023年、ダイハツの認証不正問題も“外部機関”への通報が問題の発端となった。
ダイハツには監査部が運営する「社員の声」という制度があった。しかし、匿名通報は信ぴょう性が低いとされ結果通知は行われず、また、多くの案件が当該事案の発生部署に差し戻されていたという。第三者委員会の報告書はこうした運用が内部通報制度への不信を招くとともに会社の自浄作用に対する疑念を強めたと指摘する。そのうえで、従業員が不正行為に及んだのは「短期開発への強烈なプレッシャーに追い込まれたため」であり、現場が「経営の犠牲」になったと断じる。短期開発の箇所を“予算達成”“再稼働”に置き換えればニデック、中部電力にそのまま当てはまるだろう。
2025年、中日本高速道路は2012年の笹子トンネル崩落事故後に社員から聞き取った事故原因に関する内部資料を遺族に開示した。「安全に対する根拠なき自信過剰」「予算の都合で安全対策が先送り」といった現場の声が記された資料は、遺族からの開示請求に対して10年余にわたって「ご要望の資料は存在しない」と説明されてきた。森友学園問題における財務省の対応と重なる。2026年、改正公益通報者保護法が施行される。通報を理由とした懲戒や解雇など通報者に対する不利益待遇は刑事罰の対象となる。制度の適切な運用は言うまでもない。とは言え、まず取り組むべきは個々の組織のガバナンス強化であり、ここが現場と経営、個人と社会との信頼を回復する起点となる。問われるのはトップの資質そのものということだ。
今週の“ひらめき”視点 1.4 - 1.15
代表取締役社長 水越 孝
【短期集中連載】生成AI/AIエージェントレポート発刊コラム③:『生成AIネイティブ人材くん「え、AIにやらせればよくないですか?」 』
先日、朝日放送の探偵ナイトスクープを見ていたら、中学生が生成AIを使いこなしていた。勉強だけでなく、日常の相談にも利用しているという。将来的には生成AIネイティブ世代とでも言われるのだろうか。
近い将来、こうした人材が企業に勤めることになる。いま地道に入力しているような作業も、彼らが見たら「え、AIにやらせればよくないですか?」と言うかもしれない。至極もっともであり、AIで代替できるなら自動化すればよいのだから反論の余地はない。
生成AIが日常の一部である彼らに「こんな非効率な会社でやってられるかよ」と思われないよう、組織側も変わっていく必要がある。若手人材の確保という観点でも、生成AIの活用を推進する価値はあると感じる。
【短期集中連載】生成AI/AIエージェントレポート発刊コラム②:『自律的に動くAIエージェントって頭痛が痛いみたいになってない? 』
2025年はAIエージェント元年と言われている。生成AIの盛り上がりと共にAIエージェントへの注目も高まった。2024年の調査でも既にエージェントに係る話は多々あった。当時は、自律的に業務をこなす存在として期待されていたと記憶している。基本的な考えは変わっていない一方で、わざわざ“自律的”と紹介されるAIエージェントも存在する。「ん…?そもそもAIエージェントって自律的に動くのでは?」と思ってしまう。
AIエージェントに明確な定義がないこともあり、市場には様々なAIエージェントが存在している。中には対話型AIと何が違うのかよく分からない、ということもしばしば。「自律的」という言葉は便利である。従来どおりプロンプトを入力するだけでも、多少“おまけ”が付いた出力が返ってくると、指示していないことまで自律的に実行してくれるように見えてしまう。
だからこそユーザは、「AIエージェント」という名称に引っ張られるのではなく、サービスとしてできることとできないことを整理したうえで利用していく必要がある。
【短期集中連載】生成AI/AIエージェントレポート発刊コラム①:『「生成AI!業務を効率化してくれ!!」で何とかなるわけがない 』
レポート作成にあたり事業者に取材を実施している。そうした中で、生成AIを魔法か何かと感じているユーザは一定いると聞くことがあった。調査をしていると分かるが、生成AIを実装した事例は増えてきている一方で、業務の完全自動化の実現はまだ先の話である。一方でインターネット上には生成AIの様々な未来が綴られており、これらを来月には実現するのではないかと期待する人がいる。インターネットリテラシーとは難しいものだが、何でもかんでも真に受けてしまうのは考え物である。
ここまでインターネットに踊らされていないとしても、他社事例を参考に生成AIを導入しようとした場合、背景にはデータの整備、従業員のリテラシー、業務フローなど様々な要因が重なっている。「生成AIを導入したから業務効率化できるよね!!!」とはならない。問題は、上層部のリテラシーが不足している場合である。
「A社を見習ってわが社でも生成AIを経理部門で導入してみよう。DX担当くん、よろしく頼むよ!」。DX担当くんは生成AIに詳しいとは限らない。事例やサービスをもとに自社に当てはめてみるが、A社のように成功しない。
生成AIで業務効率化するのではなく、まず業務のどこにムリ・ムダ・属人化があるのかを切り分け、そのうえで、打ち手として生成AIが有効かを判断すべきである。業務効率化の検討を進める過程で、どうやら生成AIが有効らしい、という思考を持たないといけない。
【今週の"ひらめき"視点】2026年、世界と未来への信頼をつなぐために
当社代表が最新のニュースを題材に時代の本質、変化の予兆に切り込みます。
新年おめでとうございます。年頭にあたり謹んでご挨拶を申し上げます。
トランプ2.0の最初の1年が終わった。不法移民を排除し、脱炭素を嘲り、多様性を拒否し、世界を相互関税で恫喝する。パリ協定、世界保健機構(WHO)、国連人権理事会、ユニセフからの脱退を表明し、米国の対外援助を担ってきた米開発局(USAID)を解体した。
国内では民主党の支持率が高い主要都市に対して「治安の悪化」を理由に軍を投入、政権に批判的な言論を展開する大学やメディアを「国家安全保障上の脅威」として排斥する。
トランプ氏の王様ぶり、政権の強権化は、恐らく多くの米国人が共感した“MAGA”(米国を再び偉大に)の政策理念とは別の次元にある。もはや自国第一主義の一線を越えており、米国の民主主義そのものが“フェイク”の危機に瀕しているということだ。
米中対立の中、リスクを抱合しつつ成長するASEANとの連携強化を
世界で分断が深まる中、多国間主義への信頼が揺らぐ。企業を取り巻く外部環境はますます不安定になると同時に事業活動における地政学的な制約が強まる。
自由貿易の理念が遠のく中、皮肉にも中国がその擁護者として名乗りをあげる。昨年10月末、APEC首脳会議に出席した習近平氏は、米国を念頭に保護主義への懸念を表明するとともに多国間貿易の重要性を訴えた。
実際、2025年1月-11月における中国の貿易黒字は1兆758億ドル、▲18.9%と大幅減となった米国向けの輸出額をASEAN、EU、アフリカへ分散させ、補った。伸長率はそれぞれ+13.7%、+8.1%、+26.3%、貿易黒字は2年連続で過去最高を更新する勢いである。
もちろん、最大の輸出先である対米輸出マイナスの損失は大きい。しかしながら、トランプ氏が仕掛けた関税戦争は結果的に中国に新たな成長機会を与えたとも言えよう。一方、米国もまた中国依存の低減をはかる。輸入元の切り替え先はやはりアジアである。
とは言え、アジアと中国、アジアと米国との関係はいずれもウインウインとは言い難い。安価な中国製品の大量流入は成長途上にある国内産業にとっての脅威であり、一方、対米輸出の拡大は米国にとって貿易収支の悪化を意味する。2025年1月-7月、ベトナム、タイ、マレーシア、インドネシアに対する米の貿易赤字は前期比1.5倍に拡大している。
“赤字”はトランプ氏の嫌うところであり突然の追加関税といった制裁措置への警戒も高まる。
一方、日本企業にとっても米中が最大のリスク要件である。米国の対外政策は依然として安定しないし、中国との関係にも亀裂が入った。とは言え、コロナ禍を契機に大手企業の危機対応力は強化されており、多くの企業で事業ポートフォリオの再構築が進んでいる。一定の時間を要するとしても克服は可能であり、中立的で安定的なパートナーシップを前提にアジアが抱える構造問題の中に新たな事業機会を見出してゆきたい。
成長への希望と成果の共有に向けて、大企業は旧来の取引構造の見直しを
昨年末、日銀は物価の安定と賃上げの継続的な実施を促すべく政策金利を0.75%へ引き上げた。しかし、実勢金利と比較すると依然として緩和的な水準であり、成長型経済の実現のためには賃金水準の持続的な引き上げが不可欠である。政府の掛け声もあり、産業界の賃上げ機運は高い。
しかしながら、労働分配率は依然として低く、2024年末、企業の内部留保の総額が636兆円と過去最高を更新する一方、労働分配率は53.9%、1973年以来の低水準にとどまる。すなわち、マクロ的には賃上げのポテンシャルは十分にあるということだ。問題は中小企業、彼らに財務的な余裕はない。
日本商工会議所によると、7割を越える中小企業が賃上げを予定しているものの、うち6割は業績改善がみられない中での“防衛的賃上げ”であったという(調査期間:2024年4月-5月)。そもそも多くの中小企業は大企業を頂点とする連鎖的な下請構造の中にあって公正な利益配分の埒外にある。否、そればかりか、依然として下請法における指導件数が年間8千件を超えるなど(令和6年度)、優越的な立場にある大企業と下請企業の取引構造は本質的に変わっていない。2026年3月期も上場企業の多くが好決算を見込む。異次元緩和の後遺症から日本経済を脱却させるためにも、大企業には是非ともサプライチェーン全体利益の底上げを実現していただきたい。
米オープンAI社がChatGPTをリリースして3年、世界の景色は一変した。ディープフェイク、知的財産権、セキュリティ、ガバナンスなど、もろもろの課題を抱え込みつつも、もはや後戻りはない。未来が突如として手元に引き寄せられた感がある一方、その先の未来への確信は遠のく。今、漠とした不安とイノベーションへの期待が交差する。そして、前者に現実の格差と閉塞感が重なる時、日本もまたトランプ的なポピュリズムに覆われかねない。
未来への信頼をつなぐために私たちはどう行動すべきか。フェイクを排し、事実を根拠とした多様な言論空間を維持し、多国間主義への信頼を回復すること、ここが私たちの自由で、豊かな活動をつなぎとめる起点であり、また、前提条件である。
本年もご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
今週の“ひらめき”視点 2026.1.1
代表取締役社長 水越 孝
「都築電気、OBD型デジタコを「TCloud for SCM」オプションサービスとして提供へ」
都築電気は2025年12月24日、クラウド型動態管理サービス「TCloud for SCM」のオプションとして、日本初となるOBD型デジタコを2026年4月より提供すると発表した。
都築電気、日本初のOBD型デジタコを「TCloud for SCM」オプションサービスとして提供決定|2025年|都築電気株式会社
------------------
都築電気の「TCloud for SCM」は、スマートフォンを中心とした動態管理サービスであり、白ナンバー車両や軽車両にも対応できる点が特長である。リアルタイム動態管理や日報の自動作成など、従来のデジタコでは対応しづらい領域をアプリでカバーし、操作レス記録や導入しやすい料金体系など、現場で求められる機能を備えている。
今回の OBD 型デジタコは、この“スマホ主体の運行管理”を補完するオプションという位置づけであろう。OBDⅡは本来、車速・回転数などの CAN データを精度高く取得できるため、スマホだけでは取り切れなかった車両情報を補強できる点が特徴といえる。
今回個人的に特に注目したいのは、
・走行/停車などの状態判定を OBDⅡ でどこまで自動化できるのか
・スマホの GPS・センサー情報とどのように統合されるのか
・操作レス記録がさらに広がるのか
といったポイントである。
スマホ主体の動態管理は導入しやすい一方で、車両データの精度や取得範囲では専用デバイス型に劣る場合もある。その弱点を OBD 端末で補完する今回の発表は、TCloud for SCM が“スマホだけのソリューション”から、より高精度な運行管理にも対応できるモデルへ進化していくことを示していると捉えることができる。また、“挿すだけで使える” OBD 型は工事が不要で導入しやすいため、中小企業にとっても検討しやすい選択肢となるだろう。
2026年4月の提供開始後、スマホアプリとの組み合わせによってどの程度の精度・利便性・負荷軽減が実現されるのか。こうした点が実際のユーザーにどのように受け止められるのかも含め、今後の動向を見ていきたい。
【ITユーザトレンド調査(2025)公開】
JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)がITユーザトレンド調査(2025)を公開しました(https://home.jeita.or.jp/it/publications/2512.html)。
矢野経済研究所も調査に携わらせて頂いています。
本調査は2004年度から行っている調査で、今回は、この10年余りの間に浸透したクラウド、IoTといったネットワークベースでのIT利用、さらには「生成AI」を中心とした、AIの利活用動向や導入効果について分析することを目的としています。
無料でダウンロードが可能ですので、今後の情報システム構築/運用の参考にぜひご覧ください。
YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。
YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。