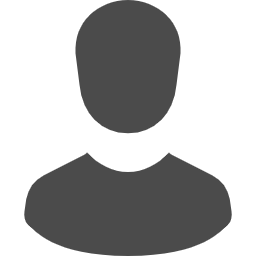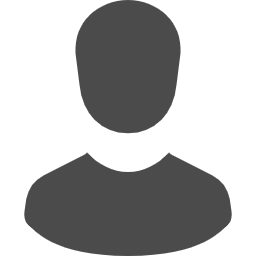デイリーコラム
SMBCとSBIが提携 Olive強化に向け新会社設立
6月16日、SMBC グループ(三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行、SMBC日興証券、三井住友カード)とSBIグループ(SBI ホールディングス、SBI 証券)は、SMBCグループの総合金融サービス「Olive」の資産運用機能強化を目的に業務提携契約を締結。新たな資産運用サービスの企画・提供を行う準備会社を設立することを発表した。「Olive」において最上位ランク「Olive Infinite」を新たに設け、資産運用において、より高度なサービスの提供を目指す。準備会社の設立は2025年7月、Olive Infiniteの提供は2026年春を予定している。
https://www.smfg.co.jp/news/pdf/j20250616_01.pdf
https://www.sbigroup.co.jp/news/2025/0616_15506.html
両グループは2020年4月に戦略的資本業務提携を締結しており、本業務提携はこの延長となる。SBI証券における三井住友カードを利用したクレカ積立サービスは月間850億円を超える規模まで成長し、協業の効果は高いとみえる。Oliveにおいては、本提携以外にもさまざまな連携・協業が発表されており、SMBCグループとして注力していく方針が伺える。(石神 明広)
NTTコミュニケーションズ、データ利活用マーケティング支援を本格展開
NTTコミュニケーションズ(以下NTT Com)は6月4日、NTTドコモ(以下ドコモ)が保有するデータを活用し、企業や自治体に対するマーケティング支援事業を本格的に展開すると発表した。データの収集・分析や施策立案、改善まで一貫して取り組む。
背景には、データやAIを活用したマーケティングのニーズの高まりがある。デジタルツールの利用が一般的となり、ユーザーごとのデータ収集が可能になった一方、利活用のノウハウを持った人材が不足しているという。こうした状況を受け、具体的には▽マーケティング戦略の策定支援▽顧客データ基盤構築▽顧客や市場の分析▽顧客接点の高度化-の4つのフェーズで支援する。
NTT Comによる支援の特長の一つとして、ドコモの保有するデータを用いた顧客分析が挙げられる。具体的には、クライアントの持つ顧客データと、1億人規模のdポイントクラブ会員のデータを掛け合わせてインサイトを導き出し、より効率的なアプローチを検討するという。また、携帯電話の基地局運用データを基に人流などを推計する統計データ「モバイル空間統計」もドコモグループならではのサービス。一定エリアにおける国内居住者や訪日外国人の人口増減を調べることができ、観光客の宿泊の有無や、イベント来訪者の属性などの調査に活用できるという。
実際にNTT Comは今年3月から、広島県観光連盟、早稲田大学、インテージ、電通総研と共同で、広島県の観光マーケティングの実証実験を実施。モバイル空間統計でインバウンド客の動態把握をした結果、イタリアやスペインからの来訪率が高いものの、約3割が日帰りしていることが判明した。同観光連盟では今後、この2カ国を対象に宿泊者の誘客に向けた施策を検討するとしている。
NTT Comビジネスソリューション本部事業推進部の徳田泰幸マーケティングインテグレーション推進室長は「NTTグループで保有する知見を活かし、効果的なマーケティングを実現していきたい」と話している。(川口 御生)
「あいおいニッセイ同和損保ら3社、レンタカー事故削減への実証実験を開始」
あいおいニッセイ同和損保、トヨタレンタリース札幌、ナビタイムジャパンの3社は、テレマティクス技術を活用したレンタカー事故削減の共同実証実験を2025年5月26日より開始したと発表した。背景には、訪日外国人の増加や国内の観光需要の回帰によってレンタカーの利用が増加し、レンタカー事故が増えていることがある。年間5000件超のレンタカー事故対策は喫緊の課題となっている。
本実証では、あいおいニッセイ同和損保のテレマティクス自動車保険「タフ・見守るクルマの保険 NexT」をベースにした「レンタカー版 NexT アプリ」を活用する。安全運転度合いに応じたインセンティブ提供で事故削減効果を検証する。
-----------------------
テレマティクスを活用した安全運転診断は今後の事故予防には有効であると考える。
他方、訪日外国人によるレンタカー利用という点に注目したい。訪日外国人にとって、標識の違いや左側通行など日本特有の交通ルールに不慣れなことが事故の一因となる可能性が高い。
今回アプリを活用するのであれば、多言語機能を備え、「運転後」だけではなく「運転前」のルール理解を促す仕組みをレンタカー貸出時に組込むのも一案だろう。そのうえでテレマティクス技術と補完しあうことで、より一層、事故予防に寄与する可能性があるのではないだろうか。(小田 沙樹子)
高臨場のライブビューイングを実現、NTT Comとヤマハが新技術
NTTコミュニケーションズとヤマハは5月28日、臨場感の高いライブビューイングを実現する共同開発技術「GPAP over MoQ」の実証実験を実施した。遠隔地でもライブ会場と連動した舞台演出が可能になるほか、音声などを転送する際の遅延を最小0.1秒程度に抑えることができる。
背景にあるのは、映画館などで配信するライブビューイングの市場規模の拡大だ。注目を集める一方、配信時に主に衛星通信などを利用するため、映像や音声を転送するとライブ本会場との間でタイムラグが生じ、双方向でのやり取りが難しい現状があった。
「GPAP over MoQ」はこうした課題を解決する。ヤマハの開発システム「GPAP」、NTTコミュニケーションズの研究するメディア転送技術「MoQ」を組み合わせている。
具体的にはGPAPは舞台演出に関するデータをwav形式に統一し、記録・再生する。従来、音声や照明といったデータは異なるフォーマットで保存していたため、複雑な信号処理を必要とするシンクロ再生はハードルが高かったという。他方、MoQは次世代プロトコルで、インターネットを利用し配信すると発生する3秒程度の遅延を抑えることができる。こうした二つの技術を掛け合わせることで、ライブ会場と同様の空間を遠隔地でも再現し、コール&レスポンスができるようになる。
同日、ヤマハ銀座店で行われた実験では、実際に同店内の2会場をつないで音楽ライブ配信を行った。観客の手拍子やコールも演奏とほぼずれることはなく、演奏者も「距離や場所の制約を越えて空気感を共有できた」と感想を示していた。
今後NTTコミュニケーションズはMoQのW3C/IETFでの国際標準仕様化をめざすとともに、26年度中の有償提供に向けて取り組んでいくという。ヤマハはGPAPを利用したこれまでの実証実験から、双方向でのコミュニケーションに対する反響の高さに注目。「コミュニケーションという文脈で、より付加価値を高めていきたい」としている。(川口 御生)
「iPhoneへのマイナンバーカードの搭載が開始」
6月6日、デジタル庁は6月24日からiPhoneへのマイナンバーカードの搭載が利用開始となる予定と発表した。android端末では既に2023年5月から可能であり、両端末においてスマートフォンへのマイナンバーカードの搭載が可能となる。これによりコンビニでの証明書の取得やマイナポータルへのログインなどがスマートフォンのみで利用できる。
https://services.digital.go.jp/mynumbercard-iphone/news/79897b6ef9f29d5b27a3d/
マイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンのみで認証や手続きが可能となる点は利便性向上につながるであろう。一方で利用可能な場面が少ない点が課題と考える。現状は証明書の取得やマイナポータルのログインが主な利用場面であるが、多くの人の場合年間で数回発生する程度の手続きである。数回程度であれば、従来通りカードをかざす方法で問題ないと考える人も多いだろう。デジタル庁はマイナンバーカードのICチップを読み取ることで対面時本人確認が可能となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」を提供するなど、利用場面の拡大に取り組んではいるが、普及にはまだ時間を要するとみる。(石神 明広)
セールスフォース・ジャパン、「Tableau Next」を日本語で提供開始
セールスフォース・ジャパンは6月15日から、エージェント型の分析プラットフォーム「Tableau Next」の日本語での提供を始める。AIエージェントを活用し、データの収集・可視化、インサイトの獲得からアクションの実行までを迅速に推し進める。
Tableau Nextは「Hyperforce」基盤上に構築されており、AIエージェントプラットフォームのAgentforceと、Tableauセマンティックの二つを中核技術に据えている。加えてData Cloudと連携しているため、統一されたビジネス定義に基づくデータ分析ができる。
特徴の一つとして、ユーザーのタスクをエージェント型で支援する点が挙げられる。利用者からの自然言語の質問に対し関連データを分析してインサイトを導くほか、データの収集・可視化といったAIスキルを備える。プレビルドの分析スキルを提供することで、意思決定の質やスピードを高めるとしている。
データレイヤーに関しては、顧客が保有するあらゆる情報を活用することができる。Snowflakeなどと連携し、外部のデータをゼロコピーで取り込むことができるため、企業の情報システム部門の担当者などは、データの複製や管理の手間を省ける。
5月26日に開かれた記者発表会で、セールスフォース・ジャパン常務執行役員Tableau事業統括本部長の福島隆文氏は、技術革新によりAIがインサイトからアクションまでを提示できるようになる中、データの信頼性向上や、データと人をつなぐ中間層(セマンティックレイヤー)の役割が重要になっていると指摘。TableauとAgentforceの連携の意義を説明し「企業はデジタルレイバーを駆使し成長を期していくことが求められる。その実現に向けた支援をしていきたい」と述べた。(川口 御生)
「SBI日本少短、バイク・自転車向けの車両専用保険が2万件突破を発表」
SBI日本少額短期保険は、2025年4月末時点において、バイク・自転車向けの車両専用保険の保有契約件数が2万件を突破したことを発表した。これは、バイク・自転車向けという比較的ニッチな商品分野において注目すべき実績であり、同社では商品特性とユーザーからの支持が背景にあると説明している。
同社は2014年からバイク・自転車を対象とした車両保険の分野に対して保険提供を開始し、約10年間にわたり多様なニーズに応える商品を展開してきた。特に、事故や盗難時に購入時からの経過年数にかかわらず購入金額を全額補償すること、そして水災被害による車両への補償を行う「車両水災特約」の提供が特徴となっている。これらの商品設計によって、同社の保険は多くのバイク・自転車ユーザーから高い評価と支持を得ているとしている。
SBI日本少短、車両専用保険の保有契約件数2万件を突破(SBI日本少額短期保険)|ニュースリリース|SBIホールディングス
今回のニュースは、まさにニッチマーケティングの成功事例といえる。バイク・自転車という限定的なユーザー層に特化し、さらにハーレーダビッドソンなど特定ブランドのユーザー向けの保険も展開するなど、明確なターゲット戦略が功を奏している。
また、事故や盗難時の購入金額全額補償や、水災特約の単体加入を可能にした商品設計は、ユーザーの潜在的な不安やニーズを的確に捉えたものである。こうした取り組みが、10年という歳月をかけて着実に成果へと結びついたのだろう。
2万件という契約件数について、10年という期間を考慮すると評価が分かれる可能性もあるが、特定ユーザー層に焦点を当てた戦略の有効性を示す事例として評価したい。今後も、こうしたニッチ市場における保険商品の動向には注目していきたい。(小田 沙樹子)
「富士通『1FINITY T900』による長距離・低消費電力伝送の実証結果から見る IOWN/APN 構想への実装的接近」
富士通は、フランスの通信事業者Orange S.A.(以下、Orange)との共同実証を通じて、自社の光伝送装置『1FINITY T900』が、約1,600kmの長距離にわたり800Gbpsの伝送速度を維持しつつ、消費電力を150W未満に抑制できることを確認したと発表した。
https://pr.fujitsu.com/jp/news/2025/06/04-01.html
Orangeは、かつて国営企業であったフランス・テレコムから民営化されたフランス最大級の通信事業者であり、欧州・アフリカ・中東にわたる広域通信サービスを展開している。現在は、5G・光通信・DX、持続可能性分野に積極的に投資しており、複数のグローバルベンダーと連携しながら次世代ネットワーク技術の導入を進めている。
本実証は、Orangeの実環境研究インフラにて実施され、富士通は伝送速度条件全てにおいて装置の電力効率が安定していたと説明した。対象装置は、保守性と運用信頼性を確保しつつ、密閉型水冷システムを採用することで冷却効率を向上させる構造を持つ。また、波長あたり最大1.2Tbpsの伝送能力や多様なイーサネット・インターフェースへの対応のような技術的要素は、伝送性能の向上および到達距離の拡大に寄与する可能性があると考えられる。
また、本装置はIOWN Global Forumが提唱する「オール光ネットワーク(APN:All Photonics Network)」構造との技術的互換性を有するとされる。IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)とは、NTT社が主導する次世代通信インフラ構想であり、ネットワーク伝送のみならず、情報処理および制御全体に光技術を適用することで、超低遅延・低消費電力・大容量通信の実現を目指している構想である。APNは、その中核をなす要素技術の一つであり、ネットワークの端点間をすべて光信号で接続することで、従来の電子系ネットワークにおけるボトルネックや遅延の削減を図る構成となっている。
さらに、富士通は、ネットワークプロダクト事業を承継する新会社「1FINITY株式会社」を2024年7月1日付で発足させ、ネットワーク関連事業を統合する方針を示している。今回の実証により、同社装置がIOWN構想の技術的方向性と整合する可能性を示唆する一方で、実際の商用ネットワークへの適用に向けては、ソフトウェア層の統合、他社装置との相互運用性、運用ポリシーへの柔軟な対応など、複数の条件下での追加的な検証も今後の課題であると考えられる。
とりわけ、ネットワーク構造全体の転換を実現するためには、複数機関の協調による実証蓄積と、多様な運用環境における検証事例の積み重ねが不可欠である。また、政策的観点からも、本装置の性能がAPN/IOWNベースのネットワーク転換に実質的に寄与し得るかを評価するための中長期的な視点での分析と検討も、今後の重要な観点となると考えられる。(曺 銀瑚)
NTTデータ経営研究所、「心の健康」投資拡大に向け、共同事業体を設立
2025年6月5日にNTTデータ経営研究所、シード・プランニングは、産官学のステークホルダーと共に「心の健康」投資拡大に向けた共同事業体の設立を支援することを発表した。共同事業体は2025年7月に一般社団法人として設立される予定になっている。共同事業体は、企業が直面する人や組織の課題を可視化や「心の健康」投資の意義・価値の啓発に取り組む。また、「心の健康」に係るサービスについて効果に関する根拠の蓄積や品質に関する情報開示の促進を目指す。
https://www.nttdata-strategy.com/newsrelease/250605/
現在、企業が従業員向けにストレスチェックを実施するのは一般化している。では、企業の「心の健康」投資は十分なのかというと疑問である。しばしば学生時代の友人に会うが、精神疾患による休職や退職は珍しくなく、企業における十分な対策が取れていないように感じる。リリースにもある通り、ストレスチェックを実施している企業は増えたもののコンプライアンス上の取組に留まっているケースは多い。そうした取り組みだけでは従業員の心の不調を予防できるとは思えず、結果として精神疾患患者の増加につながっているように感じる。
近年では従業員の心の健康の管理にAIやデータ分析を活用するサービスが増えている。投資に積極的な企業はこうしたサービスも利用しているのだろう。しかし、心の状態を管理する点において具体的な効果を測ることは難しく、投資対効果が示しにくいのが課題である。
人口減少により、従業員不足が深刻化している昨今において企業が「心の健康」投資をしていくことは必須になる。まずは取り組みが不十分な企業への啓発が求められる。加えて、今回の共同事業体の活動のように単なる投資ではなく、投資効果を裏付ける根拠の蓄積や品質情報の公開を進める意義は今後さらに高まっていくと見込まれる。
「みんなの銀行のフルクラウド型銀行システム、三菱UFJ銀行へ初の外部提供が決定」
みんなの銀行は5月27日、同行のフルクラウド型銀行システムが三菱UFJ銀行が新設するデジタルバンクの基幹システムに採用されたことを発表した。このシステムは、みんなの銀行の基幹システムを開発・運営するふくおかフィナンシャルグループ傘下のゼロバンク・デザインファクトリーとアクセンチュアによって開発された、Google Cloud 上で稼働するフルクラウド型の銀行システムである。デジタル専業銀行であるみんなの銀行向けに開発したものをベースとしており、2022年より国内外の金融機関および新たに銀行サービスの導入を目指す非金融事業者に向けて提供を開始している。
https://corporate.minna-no-ginko.com/information/corporate/2025/05/27/687/
みんなの銀行はデジタルネイティブ世代をターゲットとし、スマホアプリで完結する銀行サービスを提供している。スマホアプリ等のデジタル起点での金融サービス提供には各金融機関が注力しており、本システムへの関心は高いだろう。近年BaaSによる非金融事業者の金融事業への参入が増加しており、今後の広がりを期待したい。
【発刊裏話】「2025 PLM市場の実態と展望 ~製造業エンジニアリング領域を中心としたデータソリューション~」
今回発刊したレポートは、リニューアルに伴って対象ソリューションを見直しており、よりエンジニアリングチェーンにおけるデータ活用に主眼を置いて調査を行っています。そのため、これまでとは異なる切り口での本文や企業個票に仕上がりました。
CAD/CAM/CAEツール等で生まれたデータを一元管理し流通させることは、単なるデジタル化にとどまらないモノづくりの高度化、つまりDXを推進するために重要なステップです。ただし、PLMの必要性は認識されている一方で、実装が難しく思うようにプロジェクトが進まない実態もあるようです。
この状況をどのように打破できるのか。加えて、モノづくりの高度化実現にあとどれくらいの猶予が残されているのか。それはIT技術が急速に進展する中で、あるいは数年のスパンなのかもしれません。今回の取材でも、ベンダ各社の意欲的な姿勢が印象的でした。ベンダ・ユーザの取組が奏功し、製造業がこれまで以上に発展した近未来の到来が今から楽しみです。(佐藤 祥瑚)
【アナリスト便り】「2025 PLM市場の実態と展望 ~製造業エンジニアリング領域を中心としたデータソリューション~」を発刊
2025年6月25日に「2025 PLM市場の実態と展望 ~製造業エンジニアリング領域を中心としたデータソリューション~」を発刊しました。
本レポートは、これまで長年発刊している「PLM市場の実態と展望」のリニューアル更新版です。
PLM/PDMおよびビューア/DMUソリューションからなるPLM市場は、引き続き拡大しております。
DXの認知やデータ利活用の意識が広く普及したことで、PLMソリューションが改めて注目されており、ベンダ・ユーザ各社において積極的な取組が進んでいるようです。
また今回の取材では、PLMソリューションにおけるAI・生成AIの組込みが特に大きなトピックでした。PLMソリューションとしてどのように生成AIを活用するのが良いか、ベンダによる検討を経て、機能に落とし込まれ実運用するフェーズに入っています。
本レポートでは、PLM市場の現況および将来展望をエンジニアリングデータの流通・活用を軸に分析しました。ぜひ、マーケット研究や事業戦略の検討、製品選定にお役立てください。(佐藤 祥瑚)
「セーフィー、神奈川県藤沢市において駅前広場の再整備に関する検討材料を提供」
セーフィーは2024年10月1日~11月2日に藤沢市においてウェアラブルクラウドカメラ「Safie Pocket2」と、映像解析AIを融合した調査サポートサービス「Safie Survey」を活用した実証実験を実施した。実証実験では、歩行者・車両の滞留や通行量を定量可視化した。これにより、交通量や人流を中心とした駅前の利用状況をデータ化し、駅前再整備の実現と賑わい創出の促進に必要な情報提供を行ったという。
https://safie.co.jp/news/4167/
スマートシティ事業において人流データの活用が掲げられるケースは多い。本実証実験のような日々の滞留状況を把握する取り組みだけでなく、イベント開催時に混雑状況を明らかにすることで訪問客が快適に楽しめるようするといった取り組みもある。
カメラやセンサーを設置するだけでデータを収集できるため、比較的取り組みやすい点が強みである。一方、そのデータをどう活用するかは課題になりやすい。「駅前の広場に人が集まる傾向がある」「バス停からデパートに向かう人が多いようである」、こうした結果かた新たな施策を生み出すというのは容易ではない。
技術進歩によって、様々なデータを収集できるようになった。今後はデータ活用まで含めた事業が重要になっていく。(今野 慧佑)
「Q-STARとPlug and Playの量子スタートアップ向けアクセラレータープログラム、一部支援に疑問あり」
一般社団法人量子技術による新産業創出協議会(略称Q-STAR、会員数:114社)とPlug and Play Japanは、日本国内の量子技術に関連するスタートアップ育成を目的とした新たなアクセラレータープログラムを共同で開始すると発表した。
両者は、量子分野のエコシステム強化すべく、国内外の量子スタートアップ向けに資金調達や事業開発、パートナー連携の面から事業拡大支援を実施。また、スタートアップの成長に必要なVCとの接点やQ-STARの会員である大手企業とのビジネスマッチング等を通じて、量子関連スタートアップの成長を後押しするとしている。
https://qstar.jp/archives/7403
________
本リリースに触れる前に簡単に現状を振り返っておこう。現在、量子コンピュータ領域は、ハードウェアについて、超電導やイオントラップ、中性子をはじめ、さまざまな方式間で開発競争真っ只中。使い手であるユーザー企業による活用事例として、直近では2025年3月にコーセーがFTQC(Fault-Tolerant Quantum Computer)と思われる量子コンピュータを活用しクレンジング美容液を発売するなどの事例はあるものの、大半はPoCに留まる。
他方、ソフトウェア面では、ハードウェアの方向性が不透明である以上、量子化学や量子金融、量子機械学習をはじめ、量子コンピュータを活用したソフトウェアの開発は進みずらく、一部の企業を除き日本に限らずグローバルでも量子ソフトウェアに関するスタートアップの動きは鈍いのが実情だ。
さて、本リリースについて、評価したい点と疑問符が残る点がある。まず評価したい点として、資金調達がある。先述したように不透明な状況を量子コンピュータ関連のスタートアップが勝ち残る上では、研究開発に際して莫大な調達が必要となる。
資金調達を巡っては、日本において技術評価できるVCは非常に限られており、政府や研究機関と連携したQ-STARのような存在がVCと連携し資金調達を担うことが期待される点で本取り組みを評価したい。
次に、気になる点として事業開発に係る支援がある。ハードウェアの方向性が不透明である以上、ユーザー企業側としてはPoCに留めるのが通常であり、まだまだ多くの企業は量子コンピュータの使い道について考えあぐねているのが実態であろう。ユーザー企業の足が重い状況において、実効性のある事業開発支援ができるかは疑問符が残る。
そうした意味では、個人的にはスタートアップの資金調達支援と併せて、「そもそもどのような業務において量子コンピュータが利用できるのか」を含めた利用環境づくりを進めていく必要があるとみる。例えば、環境構築に向けてQ-STAR内でのアイデアソンやハッカソンなど、ユーザー企業における活用探索に向けた取り組みも並行して実施し、本リリースにあるビジネスマッチングに繋げていくといった事業開発支援が必要ではないだろうか。(山口 泰裕)
「発注元企業から情報セキュリティ要請を受けたのは1割程度 ~IPA 中小企業の情報セキュリティ実態を調査」
2025年5月27日 IPAは「2024年度 中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査」報告書を公表した。
https://www.ipa.go.jp/pressrelease/2025/press20250527.html
中身はこれから目を通すが、ポイントを眺めると、中小企業においても基本的なセキュリティ対策(OSの最新化など))はある程度定着していることがうかがえるとしている。一方で、ルールの策定や体制など組織的に取り組む必要のあるセキュリティ対策は進んでいないとする。
また現状、発注元企業から情報セキュリティに関する要請を受けた経験がある企業は1割強程度であり、その内容は、8割が「秘密保持のための措置」だとする。このあたり、業種によって発注元企業の”睨み”の強さは異なるだろうが、意外と少ない印象だ。
当社のIT投資動向調査でも、近年、セキュリティ周りへのユーザ投資は増加傾向にあることが分かっている。マーケットとしてのITセキュリティ分野も調査を強化すべく準備していきたい(忌部佳史)
「商用移動通信電波とAI解析による屋外人流推定を、NTTと上智大学が共同実証」
https://group.ntt/jp/newsrelease/2025/05/26/250526a.html
NTTと上智大学が、商用移動通信の電波に生じる微細な変動を利用し、屋外の通行人数を推定する実証に成功した。本技術は、次世代通信規格である6Gでの導入が期待される「通信とセンシングの統合技術(ISAC:Integrated Sensing and Communication)」の有効性を裏付ける成果として評価される。ISACは、カメラや専用センサを必要とせず、プライバシーに配慮した非接触型センシングを実現でき、夜間や遮蔽物が多い環境でも対象を撮影せずセンシングが可能である点も特長である。
これまで、通行人数の把握にはカメラや専用センサの導入が不可欠であったが、本研究では移動通信基地局から定期的に送信される同期信号(基地局が端末に対して送信する制御信号であり、通信開始時に端末側の時刻と周波数を基地局に合わせるための目印となる電波)を活用することで、センサ機器を用いずに通信用の電波の伝搬情報を利用し人数情報を取得できる可能性を示した。
本実証は、上智大学四谷キャンパスの4G基地局から送信される電波を対象とし、受信信号強度(RSSI:Received Signal Strength Indicator)およびチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)の変化を解析することで、通行人数を推定する手法で実施された。
RSSIは電波の強度のみを計測する単純な指標であり、処理負荷が小さく、1秒あたり約100回の測定が可能であることから、時間変化の把握に適している。一方、CSIは周波数帯域別およびアンテナ間の振幅や位相の情報を詳細に含んでおり、豊富な空間情報を提供できるが、データが高次元かつ処理が複雑なため、1秒あたり約1回の測定にとどまる。本実証では、これらの2種類の信号の特性を相補的に活用した。また、受信信号強度とチャネル状態情報を深層学習によるAI解析を通じて時間特徴と空間特徴を抽出し人数推定を行った。さらに、屋外環境においては風や障害物など外的要因の影響を受けやすいため、データ拡張技術を導入することで過学習を防止し、汎化性能の向上を図った。
本実証は、既存の移動通信インフラそのものをセンシング装置として活用できる可能性を示したといえる。NTTは、2030年頃の6G商用化を目指し、ISACの早期実用化に向けた技術開発を継続しながら、その成果を3GPP(国際移動通信標準化プロジェクト)に提案し6GでのISAC実用化を進めている。今後、6Gが本格導入される前に、4Gや5Gネットワークを基盤とする生活密着型の無線センシング技術としての応用展開が期待される。(曺 銀瑚)
「衛星データで災害対応を加速:『日本版災害チャータ』に関する共同研究契約を締結 」
防災科学技術研究所、富士通、衛星データサービス企画、三菱電機の4者は、内閣府と企業が協力し衛星データを活用した災害対処を進める「日本版災害チャータ」の実運用スキーム高度化に向けた共同研究契約を、2025年5月15日に締結した。
「日本版災害チャータ」は、災害発生時に、日本および海外の地球観測衛星を活用して被災地を迅速に観測し、災害対応機関や自治体、民間企業などの要請に応じて解析データを提供する枠組みである。内閣府と企業が連携してこの枠組みによる情報提供サービスの開始を目指しており、実現すれば、ユーザーは被災状況を早期に把握し、迅速な初動対応や効率的な復旧・復興が可能となる。
------------
本共同研究は、官民連携により、24時間365日体制での衛星データ活用と多様なデータ解析の加速を図る取組である。自然災害の頻発・激甚化が進む日本において、広域災害時の迅速な状況把握は極めて重要だ。
私は日ごろ保険をテーマにしたレポートを執筆しているため、今回はあえて「災害×衛星データ活用」という観点から、保険会社の取組事例を紹介したい。保険業界では、大手損害保険会社を中心に、衛星画像を活用して災害状況を把握し、保険金支払いの迅速化を図る動きがすでに始まっている。
このように、衛星データを活用した迅速な災害状況の把握は、自治体や公共機関にとどまらず、保険会社をはじめとする民間企業にとっても極めて重要な情報といえる。本取組が社会実装へとつながり、実際の災害対応に貢献することを期待したい。
「NEC、セブン‐イレブンの店舗業務を効率化および高度化する次世代店舗システムを構築」
セブン‐イレブンが推進する次世代店舗システム構築において、店舗業務の効率化および高度化を目指す本格的な変革の中核を成しているのが、NECの価値創造モデル「BluStellar(ブルーステラ)」である。
https://jpn.nec.com/press/202505/20250522_01.html
従来のSIerとしての枠を超え、顧客に本質的な価値を提供する“Value Driver”へと進化するNECの戦略的姿勢が、本プロジェクトに色濃く表れている。アプリケーションからインフラ、エッジ端末、運用管理までをEnd to Endで包括することで、現場課題に即したシステム刷新を実現。特にGoogle Cloudをベースとしたフルクラウドアーキテクチャの採用により、高い拡張性と柔軟性を備えたシステム基盤が構築されている点は注目に値する。
なかでも、NECが強みとする顔認証技術の導入は、セキュリティと利便性の両立を図る象徴的な取組みである。全国の約40万人にのぼる従業員が、非接触かつ高精度な認証を通じて業務へスムーズにアクセスできるようになったことは、店舗オペレーション全体の生産性向上にも寄与する。
また、ServiceNowを用いた統合運用管理体制の構築により、マルチベンダー環境下でもシステムの一元的なマネジメントが可能となった点も評価できる。これにより、コールセンターを含む運用プロセスの効率化と可視化が進み、トラブル対応やメンテナンスの高度化にもつながっている。
NECとセブン‐イレブンの協業は、単なるIT導入にとどまらず、リテールビジネスの構造変革を見据えた先進的な取り組みとなっている。今後の展開に引き続き注目していきたい。
「政府は地方創生2.0の基本構想骨子案を公表」
政府は、地方創生2.0の基本構想に関する骨子案を公表した。政策例の一つとして挙げられているのが、関係人口の可視化を目的とした「ふるさと住民登録制度」の創設である。これは、住民票とは別に特定の地域を「第二のふるさと」として登録できる制度であり、地域が継続的に関係人口へアプローチしていくための仕組みとして一定の効果が期待される。
もっとも、制度が実装された際の運用には課題も多いと感じられる。関係人口は、観光客のような一時的な交流にとどまらず、地域とある程度の継続的な関係を築く人々を指す。私自身、旅先で「良い土地だ」と感じた地域はいくつもあるが、その後も定期的に訪れたり、名産品を継続的に購入することは少ない。関係人口を生み出すこと自体が簡単ではなく、効果的な施策を講じるには工夫が求められる。
さらに、一度つながりを持った関係人口を継続的に維持していくためには、定期的な情報発信やイベントの実施など、継続的な働きかけが不可欠である。観光資源や特産物に恵まれた地域であれば比較的取り組みやすいかもしれないが、資源が限られている地域にとっては制度を機能させるためのハードルが高くなる。
このように検討すべき事項は多いが、関係人口の創出は地方における人口減少という構造的課題の解決に資する可能性を持つ。実際、すでに一部の自治体が、観光地の活用や地域限定イベントの実施など、独自の工夫によって地域のファン層を形成しようとする取り組みを進めている。まずはこうした取り組みを積み重ね、成功事例を蓄積していくことが、制度を現実的かつ持続可能なものとする第一歩となるだろう。(今野慧佑)
「産官学連携で生成AIを活用した持続可能な橋梁管理の実現へ ~診断業務効率化や技術継承を実現する橋梁診断支援AIの実証実施~」
NTTコムウェア、長崎大学、溝田設計事務所、長崎県建設技術研究センターは、橋梁維持管理における診断業務の高度化をめざした連携を開始。2025年4月~5月にかけて、長崎県内の13橋梁を対象に、点検データを基に生成AIを活用して橋梁の健全性や所見などの診断結果案の作成を行う実証実験を実施し、その有用性を確認。本技術により、橋梁診断業務の効率化や技術継承、修繕コスト最適化に貢献し、将来的にはメンテナンスサイクル全体をカバーした効率的な橋梁維持管理の実現を目指す。
NTTコムウェア | 産官学連携で生成AIを活用した持続可能な橋梁管理の実現へ~診断業務効率化や技術継承を実現する橋梁診断支援AIの実証実施~
主要インフラの一つである橋梁の保全・管理(特に老朽インフラ)は、日本全体での課題である。現状では、道路橋梁の約4割が建設後50年以上を経過しており、この老朽インフラ対応は僅々の課題となっている。この課題解決を図る上で、IoTやAI、ドローンといったテクノロジー活用は不可避で、特に生成AIを活用した次世代保全の実現や保全業務の効率化、ノウハウ継承ソリューション等が注目を集めている。
改正NTT法 各社がコメントを発表
いわゆる改正NTT法について通信キャリアがコメントを発表した(5/21)。NTTは単独で、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルは3社共同でのコメントとなっている。
NTTはこれまで重荷になっていたユニバーサルサービス責務の緩和やNTT東西の業務規制緩和などを歓迎するとともに、グループの機動的・効率的な経営を阻害しないようコメントした。
一方、3社コメントはNTTがこれまで構築した電柱等設備類の公共性を改めて担保されたことに賛同する一方、NTTのグループ一体化について公正な競争環境を阻害するとし、慎重さ政策議論が行われるよう要望した。
https://group.ntt/jp/newsrelease/2025/05/21/250521b.html
https://newsroom.kddi.com/news/detail/kddi_nr_s-39_3922.html
---
どちらのコメントも従来より各社が主張していたもので特別なものではないが、法改正をうけ、NTTにはIOWN構想を筆頭にグローバルでの活躍が責務といってよいだろう。国内の金のなる木を太らせることに価値はない。(忌部佳史)
「PayPay、バーチャルカード『PayPay残高カード』を提供開始(05/21)」
PayPay株式会社は、PayPayカード株式会社と提携し、2025年5月21日より、バーチャルカード「PayPay残高カード」の提供を開始した。このカードは、PayPayアプリ上で発行可能であり、Visa加盟のオンラインショップでの利用が可能である。年会費は無料であり、クレジットカードのような審査は不要である。決済額は「PayPay残高」や「PayPayポイント」から即時に差し引かれ、残高を超える決済はできない。
https://about.paypay.ne.jp/pr/20250521/01/
PayPayによる決済を導入していないオンラインショップにおいてもPayPay残高で決済可能となることで、PayPayの利便性は更に向上するであろう。5月15日には三井住友カード株式会社の「Olive」との連携も発表されており、コード決済のみならず、カード決済、ポイントサービスを強化していく姿勢がうかがえる。(石神明広)
大日本印刷株式会社、日本加除出版株式会社、株式会社Hexabase(ヘキサベース)、生活者がメタバース上でAIに悩みを相談することの有効性を確認(5/21)
2025年3月、大日本印刷、日本加除出版、Hexabaseは、自治体窓口を三次元仮想空間で再現したメタバース役所において、AI相談員が住民の悩みに応える実証実験を実施した。期間中に105名が来場し、計75件の相談が寄せられた。調査では約85%がAIとの対話を自然と評価し、約65%が心理的負担の軽減を感じた。AI相談員は家庭・離婚分野を強みにしていたが、今後は対象領域を拡大し、幅広い生活課題へ対応する方針である。また、複雑な案件では内容をAIが職員へ引き継ぎ、人とAIの"ハイブリッド"な運用の実現を目指す。
https://www.dnp.co.jp/news/detail/20176724_1587.html
自治体職員の減少は深刻な課題になっている。そうした中でも現状のサービスを維持・向上させていくためにはデジタルの活用は必須になっている。国も自治体に対して窓口DXの推進を促しており、徐々にデジタル化が進んできている。申請書類の記載をなくす「書かない」、オンライン申請で完結する「行かない」、予約やキャッシュレスによる「待たせない」、案内を分かりやすくする「迷わせない」がキーワードになっている。本実証実験は住民からの相談をAIが仮想空間上で対応するという内容になっており、これらのキーワードを実現する方法になっている。
こうした利便性という点以外にもAI相談員の価値はあると考えている。AIが一次対応を担うことで相談の敷居が下がる場合があるのではないか。例えば、職員に直接打ち明けにくいプライベートな悩みでも、まずAIに相談できれば心理的負担を軽減しやすいということもあるだろう。
また、アンケートではAIカウンセラーによる空間内での相談はどう感じたかという設問を設けている。最も多い回答だったのが「実際のカウンセリングルームのような心地よさを感じた」(40%)だった。これも興味深い点である。相談だけならばチャットで十分だと思っていたが、メタバース上で実施することが利用者の安心感を高める役割を担っているようだ。これはメタバースの強みであり、将来的には内容に応じて空間や相談員のアバターを変化させることで、より相談しやすい環境を提供することも可能だろう。
職員減少が加速している現在、こうした先端技術を活用して住民サービスを向上させることが不可欠になっている。しかし、活用すればよいというものではなく、職員負担の軽減も併せて検討しなければならない。本リリースでも今後の展開として職員への相談内容の引き継ぎについて言及されている。窓口業務において住民から聞き取った内容をデジタル化しても、支援を開始するために職員が別のツールに入力し直していては負担が増えるばかりである。自治体DXではフロントヤードからバックヤードまで一貫したデジタル化という点もポイントになっていく。
「設立からたった10年で取扱残高が3,500億円を突破」
FOLIOホールディングスの取扱残高が3,500億円を突破したという。
■ニュースリリース
FOLIOとAlpacaTechによる多面的なアプローチで金融ソリューションを拡充当社グループの取扱残高が3,500億円を突破(FOLIOホールディングス)|ニュースリリース|SBIホールディングス
実は設立前から見知っているFOLIO社のニュースを目にしてついつい取り上げたくなった。きっと上記数値はただの途中経過であり、すぐに超えていくことは分かりつつも、驚異的な成長を遂げる同社について本コラムで取り上げておきたいと思う。
本コラムを目にしている皆さんはFOLIOをご存じだろうか。証券会社の方はさておき、簡単に同社のことを本リリースをベースに紹介しておこう。FOLIO社は、主に2つの事業を展開している。まず一般顧客向けにAI投資「ROBOPRO」を提供しており、トランプ大統領就任による荒れ相場ながら2025年5月12日にサービス開始来の最高値を更新したとする。
次に、こうした「ROBOPRO」をベースとした投資一任プラットフォーム「4RAP(フォーラップ)」を銀行や証券会社など向けに投資一任運用ソリューションとして提供している。これまでに運用ソリューションの一部であるAI運用エンジン(子会社のAlpacaTech社と開発)をSBI岡三アセットマネジメントや三井住友DSアセットマネジメントの提供する投資信託に対して提供するなど、導入金融機関が抱える顧客の口座・預り残高を活用した投資一任運用サービスの普及に取り組んでいる。
さて、FOLIOは私が『2017 FinTech市場の実態と展望』において初めて取り上げた。が、実は取り上げる以前から創業者である甲斐氏にはお会いしていた。某大手FinTech企業のCFOから「面白いやつがいる」と紹介を受け、設立以前に面談をさせていただいており、当時はまだFOLIOを設立する直前の時期だったと記憶している。「これは成功するだろうな」と直感した。FOLIOは2015年12月に設立なのでちょうど今年で10年。たった10年で脅威的な成長を遂げたのはさすがというほかない。
これまでに数百社に及ぶスタートアップの創業者に取材をしたり情報交換をしているが、倒産した企業や他社に買収された企業、そしてFOLIOのようにとんでもない成長を遂げた企業と、その運命はさまざま。成功の可否に関わらず、日夜生まれているスタートアップが我々の日常をどう変えていくのか、楽しみで仕方ないし、私も1社でも多く、そうした企業を取り上げていきたいと考えている。(山口 泰裕)
「KDDIのRCSサービス開始がもたらすA2P市場の転換」(5/20)
KDDI株式会社とSupership株式会社は、2025年5月20日より法人向けメッセージ配信サービス「KDDI Message Cast」を通じて、日本国内でAndroidおよびiOSの標準メッセージアプリを対象とするRCS(Rich Communication Services)の配信を開始した。KDDIによると、両プラットフォームへの同時対応は国内初であり、従来SMSを中心としてきたA2P(Application-to-Person)型コミュニケーション方式における技術的転換の可能性を示す事例といえる。
https://biz.kddi.com/topics/2025/news/019/
従来のA2P SMSは、高い開封率および到達率を背景に、マーケティング、認証、行政通知といった分野で依然として主要なチャネルとして機能している。しかしその一方で、一方向かつテキスト主体という構造的な限界も指摘されてきた。そこでKDDIは、A2P SMSの抱える課題に対する現実解として今回、RCSの配信を開始した。RCSはこうした制約を補完する次世代型のメッセージング技術として注目されており、画像や動画、ボタン型メニューといった視覚的要素や双方向インターフェースを備えている。また、応答を促すボタンや、予約・問い合わせ対応といった機能がメッセージ内で完結することで、従来のコールセンターやWebフォームを介さず、直感的な顧客行動の誘導が可能となる。さらに、企業認証機能により、セキュリティおよび信頼性の向上も期待できる。
とりわけ、金融・インフラ・物流など、「リカーリング(Recurring)」が求められる業界においては、RCSを通じて一方的な通知型から、その場でやりとりができる仕組みに変えることで、企業と顧客の関係をより実用的な形に再構築できると見込まれる。例えば、支払いの案内や手続きがその場で処理できるようになることで、企業(配信元)と顧客(受け手)の距離が縮まり、継続的な関係づくりにもつながるだろう。
RCSの商用開始は、顧客接点におけるコミュニケーション品質向上を意図した一例と捉えることができるが、一方で、個人の端末や通信環境による安定性の確保、SMSに比するコスト構造、コンテンツやユーザージャーニー設計の複雑さといった課題も存在する。今後、ユースケースの拡大とユーザーの受容状況に応じて、A2P市場におけるRCSの比重が変化していくと考えられる。(曺 銀瑚)
デジタル庁がJPKI導入事業者一覧を更新(05/16)
デジタル庁は2025年5月16日、公的個人認証サービス(JPKI)に対応する民間プラットフォーム事業者の一覧を更新した。JPKIはマイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を活用し、オンラインでの本人確認や文書の改ざん防止を可能にする仕組みである。本サービスは、銀行口座開設やローン契約など多様な民間サービスに導入されており、2025年4月末時点で717社が利用している。導入理由としては、セキュリティ強化、顧客サービスの向上、事務コスト削減といった点が挙げられる。
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/private-business/jpki-introduction
JPKIは当初、銀行等の口座開設時の本人確認での利用が大部分を占めていた。この利用方法は現在も拡大中であるが、加えてイベント、マッチングアプリでの活用事例が増加傾向にある。健康保険証・運転免許証のマイナンバーカードへの一本化の影響もなどでマイナンバーカードの普及率が高まっており、JPKIの利用場面の拡大が見込まれる。(石神明広)
「6G時代におけるネットワーク・ビジョンと実証:『Network for AI』の実現を目指したロボット共同開発プロジェクト」②
3. 「Network for AI」実現に向けたコンセプトロボット開発プロジェクト
ドコモは2024年より『6G Harmonized Intelligence』プロジェクトをスタートし、ロボット・AI・デザイン分野の多様な専門家および企業との協業に取り組んでいる。本プロジェクトは、「Network for AI」の実現に向けた初動的な取り組みであり、将来的に想定されるさまざまなユースケースの実証および技術要件の具体化を目的としている。現在、ドコモを中心とした以下の3社が、6Gの低遅延・高信頼通信技術を活用したロボットの共同開発を実施しており、今後も多くのパートナーの参加が予定されている。
・アスラテック株式会社:既存のセンサーやカメラを排除し、外部デバイスとの通信によって制御される「ハーモナイズドセンサレスロボット」を開発
・ピクシーダストテクノロジーズ株式会社(PxDT)と筑波大学:人間とAI・ロボットとのインタラクションを想定した「コンポーザーとグルーバー」を開発
・ユカイ工学株式会社:自然生態系と共生しながら自律的に行動する「DENDEN」を開発
4. まとめ
本プロジェクトは、単なる技術的性能の追求を超え、人間のコミュニケーションを模倣・補完し得る通信インフラの必要性を実証することにその意義を持つ。分野横断的な連携や通信基盤の融合によって具現化された本開発事例は、6Gの社会実装に向けた技術的実現性と制度的正当性の両面を裏付ける重要な検証事例として意義を持ち、今後の展開が注視される。
「6G時代におけるネットワーク・ビジョンと実証:『Network for AI』の実現を目指したロボット共同開発プロジェクト」①
https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_250519_c1.pdf
1. 概要
2030年頃の商用化を目標に研究開発を進めている第6世代移動通信システム(6G)は、単なる技術的進化にとどまらず、社会構造および人間・機械間関係性を根本から再定義するための基盤インフラとして位置付けられている。これに対し、NTTドコモは6Gにおける5つの価値を提唱し、中でも「AIのためのネットワーク(Network for AI)」の価値から、AI・ロボット・機械が人間と共存しながら最大限に性能を発揮できるネットワークインフラの実現を目指している。ドコモはまた、複数の企業と連携して開発した3種のコンセプトロボットを通じて、6Gにおける技術的方向性および実効性の検証を行っている。
2. ドコモが掲げる「6Gが目指す5つの価値」
ドコモは、2020年1月に『ドコモ6G ホワイトペーパー』を公表し、2030年の商用サービス実現を見据えた次世代通信システムのコンセプトを公開した。その後、国内外キャリアやベンダーとの協力を通じて、実証実験、標準化、技術要件の策定などを継続的に推進している。ドコモが提示した「6Gの5つの社会的・技術的価値」は以下である。
(1)サステナビリティ(Sustainability):IOWN(光電融合を基盤とする低消費電力・高速通信技術)およびAIによるネットワーク制御を組み合わせ、エネルギー効率の最大化とカーボンニュートラルの実現を図る。
(2)効率化(Efficiency):ネットワーク構造の簡素化、運用効率の向上、周波数資源の最適利用などを通じて、コストと性能の両立を目指す。
(3)顧客体験(Customer Experience):感覚伝達型の新しいコミュニケーション、精密な測位・センシング、障害耐性と継続性を備えた通信など、6Gならではの差別化された顧客体験の提供を志向する。
(4)AIのためのネットワーク(Network for AI):AI・ロボット・機械が自律的に学習・判断可能な環境を構築し、人と調和的に共働する「社会的AI」のネットワークレベルでの実現を目指す。
(5)コネクティビティ・エブリウェア(Connectivity Everywhere):衛星通信やHAPSなどの非地上系ネットワークと地上系ネットワークの統合により、場所を問わず安定した接続性を確保する。
とりわけ「Network for AI」は、高信頼・低遅延・多接続といった特性が要求される「超知能(ASI: Artificial Super Intelligence)」時代の中核アーキテクチャであり、単なるAI基盤を超えて、人間・機械間協働の基盤を提供する構造として期待されている。
「さくらインターネット、フルマネージドの生成AI向け実行基盤「さくらの生成AIプラットフォーム」を提供開始」(5/14)
さくらインターネットは2025年5月14日、生成AIアプリケーション向けのフルマネージド型実行基盤「さくらの生成AIプラットフォーム」の提供を開始した。
https://www.sakura.ad.jp/corporate/information/newsreleases/2025/05/14/1968219471/
本サービスは、ユーザの選択次第で基盤からアプリケーションまで、国産サービスのみで揃えることもできる。
ITに関しては海外のサービスを利用するケースが多い。日本の文化、慣習にも強いと推測される国産サービスの発展を期待したい。(小山博子)
「NEC、自然関連財務情報開示タスクフォース(以下 TNFD)レポートの作成にAgentic AIを活用すると発表」
NECは、年内に開示予定の自然関連財務情報開示タスクフォース(以下 TNFD)レポートの作成にAgentic AIを活用すると発表した(5/20)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000929.000078149.html
TNFDレポート作成業務に向けてAgentic AIを適用し、調査、リスク・機会抽出、リスク評価、執筆・レビュー、広報の5つのタスクを実行する機能を開発する。既に一部で活用しており、調査では専門ガイダンス読込にかかる時間を92%削減したという。
この取り組みはNECの「クライアントゼロ」(自社をゼロ番目のクライアントとして新技術を実践するもの)として行われる。
----
特定業務向けの生成AIサービスは次々に発表されている。今年は情報を追いかけるのも容易ではなくなるペースのようだ(忌部佳史)
YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。
YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。